社労士受験に合格した後、すぐに独立開業とまでは考えていないが、「まずは登録だけでも…」と悩んでいませんか?
そして「とりあえず登録してみようかな」と思ったときに出てくるのが「社労士その他登録」という選択肢。
でも、「社労士その他登録って何?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか?
今回は、2020年8月から2025年4月まで社労士の“その他登録”を経験し、その後開業登録へ変更した筆者しま丸ねこが、リアルな体験とともに「社労士その他登録」について徹底解説します!
この記事を読むと、社労士その他登録の実態とメリット・デメリットが明確になり、自分に最適な登録方法を選択できるようになります。
-
-
- 社労士試験合格後、開業を迷っている方
- 社労士登録を検討中の方
- 社労士受験生の方
- 会社やめたい、独立開業したいと思っている方
- 「社労士その他登録」について知りたい方
-

社労士受験に合格したので、社労士会に登録しようと思っている。ただ、まだ開業するつもりはないし、今の仕事で社労士関係の仕事もしていないので、どうしたものか?

そこで、社労士登録には「その他登録」というものがあるよ! まず登録したいだけなら、その他で登録することを勧めるよ!まずはこの「その他登録」の実態を解説しよう!
社労士その他登録の実態
社労士の「その他登録」は、商売(アウトプット)以外なら、結構色々できるよ。
特に講習会等の勉強(インプット)はほとんどできるよ。
(一部、開業登録だけしか受講できない講座もあるが(労務監査研修等))
社労士その他登録とは?

社会保険労務士(社労士)の登録には「開業」「社労士法人の社員」「勤務」「その他」といった登録の種別があります。
「その他登録」とは、社労士資格保有者でありながら、現時点で社労士業務(商売)を行わない場合に選択できる登録形態です。
(定義:社会保険労務士法および全国社会保険労務士会連合会の定めによる)
参考:全国社会保険労務士会連合会 登録区分の説明
「その他登録」は、社労士として業務を行わないが、資格を保持し社労士会に所属し続けるための登録です。
(制度の詳細は各都道府県会や全国連合会HP参照)
社労士その他登録の内容
「その他登録」のポイントを整理すると――
- 商売(アウトプット)は不可(独立開業不可)
- 講習会・勉強会(インプット)への参加はほぼ可能
- 社労士として名乗ることが可能(しかし、社労士と名乗って相談業務はできない)
- 他の会員とつながりを持てる
- 会費が比較的安い
社労士その他登録の実態(体験談)
私しま丸ねこは、2020年8月~2025年4月までその他登録を経験。その間のリアルな感想をお伝えします。
メリット
- 社労士として名乗れる
- 正規登録者として名刺に肩書を記載できる(資格保持者として周囲にアピールができ、信頼感も得やすい)
- 社労士会主催の講習会・勉強会に参加できる
- 全国社労士連合会や各地の社労士会から案内が多数届き、大半に参加可能、特定社労士の講習会、親睦会も参加OK
- 他の会員とつながりが持てる
- 新人オリエンテーション、同期会、ブロック会、地域の祭りなど、同業者コミュニティで交流し情報収集ができる
- 開業登録に比べ、会費負担が少ない(詳細は地域ごとに確認必要)
デメリット
- 商売ができない(当たり前だが、商売できるのは開業登録と社労士法人の社員登録だけ)
- 副業としても社労士業務はできない(本格的な独立を目指すなら開業登録が必須) ※いずれにしろ、副業としてやっていくのだったら、商売できないのは本末転倒
- 労務監査の実践編など、実務系の深い講習は参加不可の場合がある
- 行政協力の依頼案件に参加しにくい、開業登録でなくても呼ばれることはあるが、積極的には参加しづらい雰囲気
(社労士会から案内される行政協力に大手も振って参加しずらい、開業登録でなくても参加できる?ともいわれている様だが、グレーラインな感じで、気持ちよく参加するには開業登録するしかない) - 常連や先輩社労士の多くが開業登録者で、その他登録だと肩身が狭く感じ、会合出席もためらいがちとなる(→結局、種別変更したくなる→最終的には「やはり開業登録で…」と気持ちが傾いていく)
具体例:社労士その他登録のリアル

・社労士会主催の講習会や勉強会の案内がたくさん届く、大半に参加できるので、知識のアップデートやネットワーク作りに最適(インプットほとんどできる)(ただ、web でないリアルの講習会はだいたい平日なので、土曜日だとそんなないかなあ)
・社労士会支部の新人オリエンテーションや同期会で横のつながりが強まる、社労士会主催の親睦会にも参加可能、他の社労士の人と会合等で会い話し、業界の内情等を確認できる
(会合例)
*新人オリエンテーション:その年の新規社労士会の入会者を集め、社労士会の運営方針や活動を説明する
*同期会:新人オリエンテーションに参加した人たちが、その年の同期として親睦会に参加する(1回開かれた後はもうないかなあ・・)
*ブロック会:同じ地域の会員との会合で、一年に1~2回ぐらいある
・各地域の市民祭り等で、社労士会のPR活動にも参加できる
(ただし、行政協力や一部専門講習には参加しづらい“壁”も感じる)
・社労士会の会合では「その他登録」の肩身の狭さ、開業登録者への羨望、葛藤も……
(あくまでも個人的な感覚的なもので、その様に自分が感じただけだが・・)
ただ、会合の常連は皆さんほとんど開業登録の方、その他登録だと最初会合にきても、その内来なくなる感じ・・
社労士会参加時に先輩社労士は何かと勧誘するが、開業登録者を中心に勧誘している感じ・・
それはその他登録が悪いと言うよりも、今までその他登録だと本気でまめに社労士会の会合に参加する人が少なかったので、この様な感じになるのではないかと思う・・
まとめ:その他登録のメリット・デメリット
メリット
- 社労士として名乗れる
- 講習会・勉強会で学べる
- 他の会員とネットワーク形成可能
- 会費が比較的安い
デメリット
- 商売できない(独立開業不可)
- 一部講習や行政協力案件に参加しづらい
- 肩身が狭いと感じる場合も
どんな選択肢が自分に合うのか――
メリット・デメリットをじっくり比較し、“登録したまま様子見”も良し、“思い切って開業登録へ切り替え”も良し
ご自身のライフプランと照らし合わせて、後悔のない選択をしてください。
この記事が、これから社労士登録や開業を検討する皆さんの参考になれば幸いです

社会保険労務士です。
2022年9月に登録しました。
行政書士は登録準備中です。
まず副業から始めて、士業開業を目指していきます。
ブログも始めました。
士業を目指している方どうぞよろしくお願いします。
2025年5月に開業登録しました。
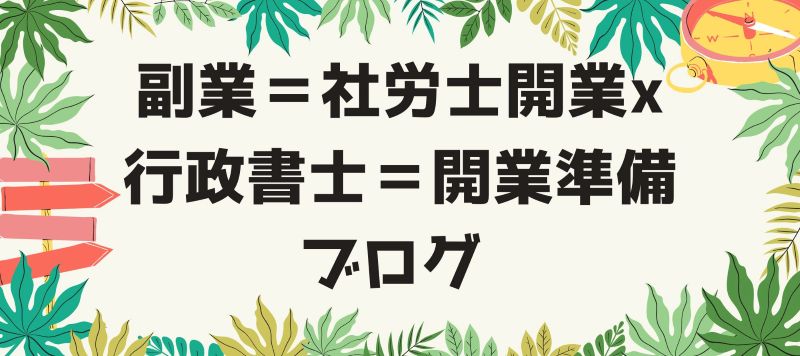




コメント