世間では上司からのパワハラが話題になることが多いけれど、そもそも上司から何か強く言われたらパワハラになるのかなあ?
明らかにそれは酷いでしょというのはわかるけど、微妙なラインはどうなのかなあ?
そもそも会社の上司の仕事の一つとして、教育、指導があるけれど、ちょっと指導するだけでパワハラになる危険があるのかなあ?
と思ったことはないでしょうか?
そこで、社会保険労務士である私しま丸ねこが、法令に絡め、パワハラ(パワーハラスメント)がどういう時に成立するのか、解説していきます。
この記事を読むとパワハラ(パワーハラスメント)のことが理解できるようになります。
・どういう状況ならパワハラになるのか知りたい方
・そもそもパワハラ(パワーハラスメント)のことを知りたい方

最近、課長になり、部下の指導をしなくてはならないが、パワハラと言われないかが心配で、まともに部下の指導ができていない様な気がする。
明らかな場合はわかるとして、微妙ば場合はどうなのかなあ?

そうだよね~?! 今回はその辺のこと、「パワハラ(パワーハラスメント)の判断基準」について、解説するよ!
パワハラの判断基準
原則として、パワハラ(パワーハラスメント)は、職場で上司から強く言わる等して、自分が(主観的に)就業環境を害されたと感じただけではパワハラにはなりません。
(客観的な意味で、就業環境が害されたと感じたかが基準となります。)
パワハラ(パワーハラスメント)とは?

パワハラ(パワーハラスメント)の定義
労働施策総合推進法第30条の2第1項と厚生労働省のパンフから
パワハラ(パワーハラスメント)は、
・職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
・その雇用する労働者の就業環境が害されること
と定義されています。
パワー(パワーハラスメント)の内容
パワハラに該当する代表的な言動の類型
1.身体的な攻撃
暴行、傷害等
2.精神的な攻撃
暴言等
3.人間関係からの切り離し
無視、仲間はずれ等
4.過大な要求
高レベル業務、必要のない業務等
5.過小な要求
程度の低い仕事
6.個の侵害
私的なことへの過度の立ち入り
参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
パワハラ(パワーハラスメント)の判断基準

パワハラは、職場で上司等から、業務上の必要性・相当な範囲を超え、された相手(労働者)が(平均的労働者の感じ方で)就業環境が害されたと感じた場合、
パワハラになります。
平均的労働者の感じ方とは、社会一般の労働者が同じ状況で同じ言動を受けた時に就業環境が害されたと感じるかどうかが基準となります。
すなわち、主観的に就業環境が害されたと感じただけではパワハラとはならないのです。
(客観性が重要となります)
参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
パワハラに関する具体例

判例:前田道路事件
営業所の事業成績を改ざんする不正経理を行っていた営業所長に対して、上司が厳しく叱責したが、パワハラ認定されなかった判例です。
(概略説明)
不正経理を行っている者は是正指示をされていたにも関わらず、是正せず不正経理を続けているので、ある程度厳しい改善指導をすることは、上司の正当な業務範囲内とされパワハラ認定されませんでした。
判例:関西ケーズデンキ事件
家電量販店の店員の社内ルール違反に対して、上司が声を荒げて叱責したが、パワハラ認定されなかった判例です。
(概略説明)
家電量販店の店員Aが社内ルールに違反して、取り寄せた商品を値引販売していた
店長Bが注意叱責した→その後配置換え
↓
店員A自殺→遺族会社を訴え
↓
店長Bの叱責はある程度強いものであったと言えるが、Aは何度もルール違反をし反省が認めららず、Aは叱責をうけてもやむを得ないとされた
まとめ
パワハラ(パワーハラスメント)の判断基準は、
・職場で
・上司等(優越的な関係者)から
・業務上の必要性・相当な範囲を超え
・労働者が
・就業環境が害されたと感じた(平均的労働者の感じ方で)
これら条件がそろった時に、パワハラになります。
そして、就業環境が害されたと感じたとは、平均的労働者の感じ方で感じたときであり、これは、社会一般の労働者が同じ状況で同じ言動を受けた時に就業環境が害されたと感じるかどうかが基準となります。
すなわち、「就業環境が害されたと感じた」の判断については、労働者の主観ではなく、客観性を重視するのです。
よって、パワハラは、された相手が就業環境が害されたと思い、パワハラだと考えただけでは、パワハラにはならないのです。
パワハラは非常に身近です。ただし、少し部下へ言っただけでパワハラになると思い、部下への教育、指導を怠るというのも問題です。通常は教育、指導の範囲ならば、パワハラにはならないという考えのもと部下と接していくべきですね。
コンプライアンスが叫ばれている中、当然管理職も労働法の知識が必要となります。
参考になれば幸いです。

社会保険労務士です。
2022年9月に登録しました。
行政書士は登録準備中です。
まず副業から始めて、士業開業を目指していきます。
ブログも始めました。
士業を目指している方どうぞよろしくお願いします。
2025年5月に開業登録しました。
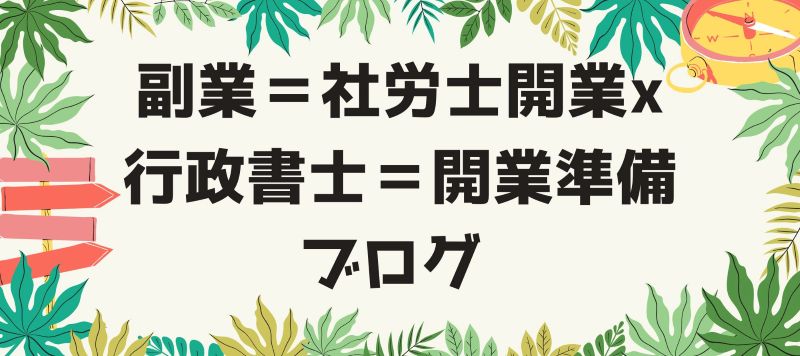
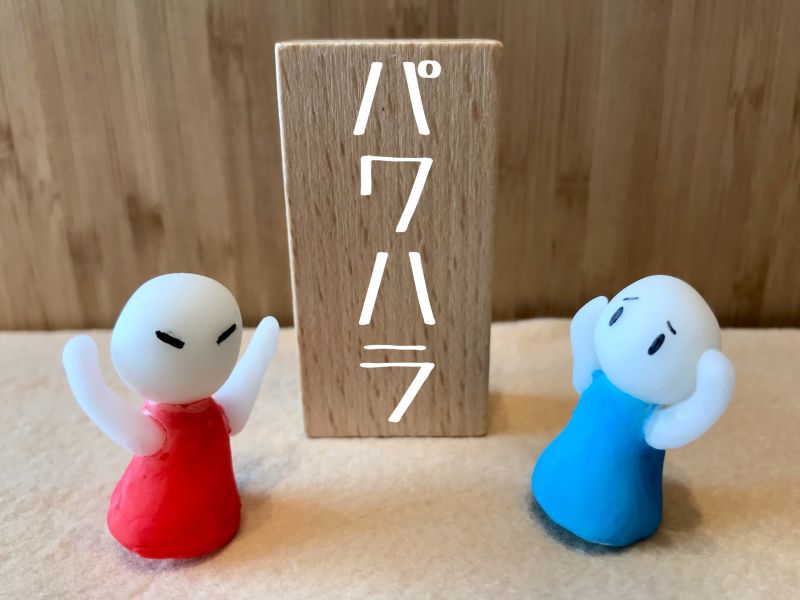

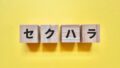

コメント